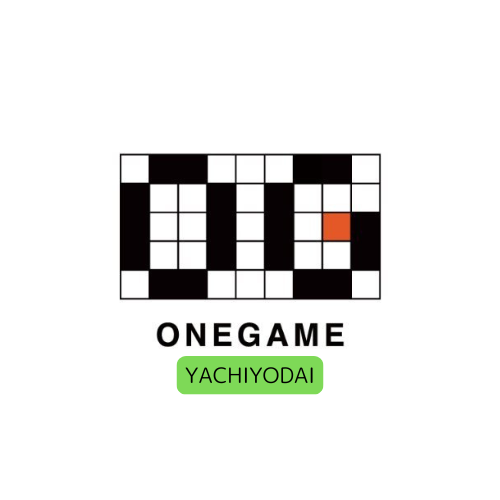みなさん、こんにちは!ONEGAME八千代台のかまちゃんです。もうそろそろ桜も開花しそうな、1年で一番好きな季節です、暑くもなく、それほど寒くもなく。筋トレも思う存分できる、大好きな春です!!
さて、当施設では就労継続支援B型として、障がいをお持ちの方が自分らしく働き、生活できるよう、スタッフ全員、毎日全力でサポートしていますが、今回は「マインドフルネス」という心の健康法について、実践方法とその効果についてお話しします。特に障がいと共に生きる方や、ご家族の方にとって役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
マインドフルネスとは?現代社会で注目される理由
マインドフルネスとは、「今この瞬間の体験に、評価や判断をせずに意識を向けること」を意味します。簡単に言えば、「今、ここ」に意識を集中させる心の技術のことです。 現代社会では情報過多やストレスにより、多くの人が不安や焦り、集中力の低下に悩まされています。障がいをお持ちの方にとっては、これらの問題がさらに大きな壁となることも少なくありません。また、引きこもり状態にあるお子さんの保護者の方も、日々の不安や心配で心が疲れ切っていることが多いのではないでしょうか。 マインドフルネスは、このような状況において心の安定と集中力を取り戻す効果的な方法として、医療や教育、ビジネスの場でも広く活用されるようになりました。
マインドフルネスが障がいのある方に役立つ理由
障がいのある方がマインドフルネスを日々実践することで、以下のような効果が期待されるといわれていますのでご紹介させていただきますね、 ・不安やストレスの軽減
マインドフルネスを定期的に行うことで、不安や緊張が和らぎ、心の安定につながります。 ・感情のコントロール
自分の感情を客観的に観察する習慣がつくことで、感情の波に振り回されにくくなります。 ・集中力の向上
「今ここ」に意識を集中させる訓練は、日常生活や仕事での集中力アップにつながります。 ・自己受容の促進
判断せずに自分を観察することで、自分自身を優しく受け入れられるようになります。 ・身体感覚への気づき
体の緊張や不快感に早く気づけるようになり、適切なケアができるようになります。 これらの効果は科学的研究でも裏付けられており、特に発達障がい、精神障がい、身体障がいなど様々な障がいを持つ方々に効果があるとされています。
引きこもりのお子さんを持つ保護者の方へ
お子さんの引きこもり状態に心を痛めている保護者の方にとっても、マインドフルネスは大きな助けとなります。なぜなら、
・保護者自身がマインドフルネスを実践することで 日々の不安や心配から少し距離を置き、心の余裕を取り戻せます
・自分の感情を客観的に見ることで、お子さんとの関わり方にも変化が生まれます
・「今できること」に焦点を当てることで、未来への過度な不安から解放され、自分自身を責めるような思考パターンから抜け出せるようになります さらに、
・お子さんと一緒にマインドフルネスに取り組むことで、新しいコミュニケーションの形が生まれる可能性もあります。
マインドフルネスの基本的な実践方法5つ
①マインドフルネス呼吸法(5分間) 静かな場所で座るか横になります、そして 目を閉じるか、やわらかい視線で一点を見つめます。それから、自然な呼吸に意識を向けます。 息が体に入ってくる感覚、出ていく感覚を観察して、心が別のことに向かったら、優しく呼吸に意識を戻します
②ボディスキャン(10分間) 横になるか座った状態でリラックスします、そして つま先から始めて、徐々に上へと意識を移動させます そのあとは、各部位の感覚(温かさ、重さ、痛み、快感など)に注意を向けます 勝手に判断せずに、ただその状態を観察します 全身をスキャンし終えたら、全体としての身体の感覚を味わいます
③ マインドフルな歩行(10分間) ゆっくりと歩き始めます、そして 足の裏が地面に触れる感覚、重心の移動、バランスを取る感覚に注目します それから、歩くたびの身体の動きを細かく観察します 周囲の音、匂い、景色にも意識を向けます 思考が浮かんでも、優しく歩行の感覚に戻ります
④五感を使った瞑想(5分間) 座った状態で、まず5つの物を「見て」意識します、そして 次に4つの物(なんでもよいです)を「触って」その感触を味わいます 3つの音(なんでもよいです)を「聴いて」識別します 2つの香り(これも、なんでもよいです)を「嗅いで」感じます 1つの味(なにがよいですかね?これもなんでもよいです)を「味わいます」(例:口の中の味) この方法は、パニック発作や強い不安に効果的です。
⑤日常生活でのマインドフルネス実践 食事しているとき、一口ずつの味、香り、食感を意識して味わう 入浴中は、お湯の温かさ、石鹸の香り、水の感触を味わう 家事をしているときは、掃除や料理の一連の動作に集中する 通勤・通学中、周囲の風景や音、体の動きを意識する
ONEGAME八千代台での取り組み
当施設では、利用者の皆さんの心と体の健康をサポートするため、マインドフルネスのグループセッションを定期的に開催しています。 セッションの内容は、専門家のガイダンスのもと、基本的なマインドフルネス瞑想を学びます。日常生活に取り入れやすい簡単なエクササイズを練習します、そして参加者同士で体験を共有し、継続するモチベーションを高めます、もちろんこれら一連の行動においては、個々の障がい特性に合わせたアプローチを提案していきます 参加者からは「心が落ち着くようになった」、「イライラが減った」、「集中して作業できる時間が増えた」などの声をいただいています。
マインドフルネス実践のコツとよくある質問
Q1: マインドフルネスは宗教と関係がありますか? A: 現代のマインドフルネスは科学的アプローチに基づいたストレス軽減法で、特定の宗教とは関係なく誰でも実践できます。
Q2: 効果を感じるまでどのくらい続ければいいですか? A: 個人差はありますが、多くの方は2〜3週間の継続で変化を感じ始めます。8週間のプログラムを修了すると、脳の構造にも変化が見られるという研究結果もあります。
Q3: 集中できない、すぐに雑念が浮かんでしまうのですが… A: それはとても自然なことです。マインドフルネスの目的は雑念をなくすことではなく、雑念に気づいたら優しく意識を戻す練習をすることです。この「気づき」自体が重要な成果です。
Q4: 障がいがあっても実践できますか? A: はい、できます。障がいの種類や程度に合わせてアプローチを調整することで、どなたでも実践可能です。当施設のスタッフがサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
マインドフルネス実践のコツ
最初は短い時間(1〜3分)から始めましょう、毎日同じ時間に実践すると習慣化しやすいです。また、スマートフォンのアプリを活用するのも良い方法です。とにかく、完璧を求めず、「練習」として取り組みましょう。通所している仲間やグループで実践するとずっと継続しやすくなります
マインドフルネスによる変化の事例
Aさん(30代・発達障がい)の場合 仕事中の集中力低下と不安に悩んでいたAさん。マインドフルネス呼吸法を毎朝5分間、3週間続けたところ、「頭の中のざわざわが少し静かになった」と実感。仕事のミスも減り、自信を取り戻しつつあります。
Bさん(50代・引きこもりの子を持つ母親)の場合 息子の引きこもり状態に強い不安と自責の念を抱えていたBさん。ボディスキャンと五感瞑想を習慣にすることで、「自分を責める思考から少し距離を置けるようになった」と話します。息子への接し方も変わり、会話が増えてきたそうです。
Cさん(40代・身体障がい)の場合 慢性的な痛みと付き合いながら生活しているCさん。マインドフルネスを実践することで、「痛みそのものは変わらなくても、痛みへの向き合い方が変わった」と語ります。痛みに対する不安や恐怖が軽減し、生活の質が向上しました。
まとめ~マインドフルネスで一歩ずつ、自分らしく~
マインドフルネスは、障がいや日常の困難と共に生きる方々にとって、心の安定を取り戻す有効な手段となります。完璧を目指すのではなく、少しずつ自分のペースで取り入れていくことが大切です。 私たちONEGAME八千代台では、マインドフルネスを含めた様々なアプローチで、利用者の皆さんが自分らしく生きられるようサポートしています。 一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。施設見学や体験利用も随時受け付けています。あなたやご家族の「今日がちょっと良くなる」お手伝いができれば幸いです。
お問い合わせ・施設見学について
ONEGAME八千代台(就労継続支援B型)では、随時見学・相談を受け付けています。
住所:〒276-0031 千葉県八千代市八千代台北1-9-9
電話:043-400-3223
メール:contact@tlife-chiba.com
営業時間:平日9:00〜18:00
障がいや引きこもりでお悩みの方、ご家族の方、お気軽にご連絡ください。マインドフルネスについての質問も歓迎します。
「今日が、ちょっと良くなる」をモットーに、スタッフ一同お待ちしています。
では、また!みんなのかまちゃんでした