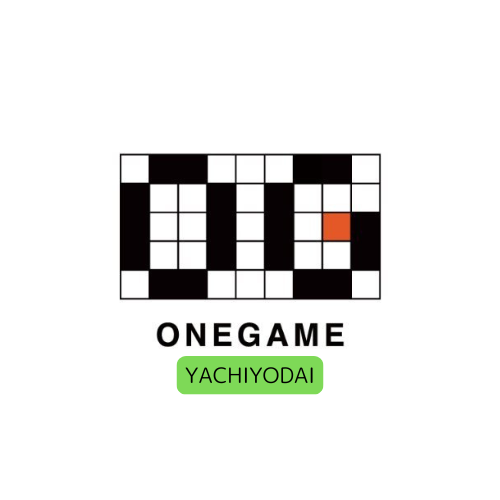みなさん、こんにちは!ONEGAME八千代台のサービス管理責任者「かまちゃん」です。今日は、30年以上にわたる精神障害支援の経験から、特に「不安障害」について皆さんにお話ししたいと思います。
不安障害に悩む方々は年々増加しており、私たちの事業所を利用される方の中にも、様々なタイプの不安障害を抱える方がいらっしゃいます。社会不安障害、パニック障害、全般性不安障害、特定の恐怖症など、その形は様々ですが、「過剰な不安によって日常生活が制限される」という点では共通しています。 本日は、現場で実際に利用者さんと共に実践してきた不安障害への対処法と、少しずつ回復していく過程でのサポート方法をお伝えします。医学的な知識だけでなく、「現場で実際に効果があった方法」に焦点を当てていますので、ご本人はもちろん、ご家族や支援者の方々にもお役立ていただければ幸いです。
不安障害とは~現場から見える「生きづらさ」~
不安障害は単なる「心配性」とは異なります。ONEGAME八千代台に通われる利用者さんの言葉を借りると、
「何か悪いことが起こるという確信が常にある….」
「不安がなくなることがない。休息がない….」
「体が勝手に反応してコントロールできない….」
このような状態が続くと、日常生活のあらゆる面に支障をきたします。仕事ができない、外出できない、人と会えない…そして、その状況にさらに苦しむという悪循環に陥りがちです。
そこで、不安障害の主な種類とその特徴を、利用者さんの実例とともに紹介していきますね、
・社会不安障害(社交不安障害) Fさん(20代男性)
人前で話すことや、他人に見られることに強い不安を感じます。ONEGAMEに来所した当初は、挨拶もできず、常に下を向いていました。「自分が何か言うと、みんなに変な人だと思われる」という恐怖感が常にありました。
・パニック障害 Gさん(30代女性)
電車や人混みの中で突然の動悸や呼吸困難に襲われます。「死んでしまうのではないか」という恐怖から、発作が起きそうな場所を避けるようになり、行動範囲が極端に狭くなっていました。
・全般性不安障害 Hさん(40代男性)
仕事、健康、家族など、様々なことに過剰な心配を抱え、常に緊張状態にあります。「何か悪いことが起こる」という漠然とした不安が常にあり、集中力の低下や睡眠障害に悩まされていました。
・特定の恐怖症 Iさん(50代女性)
エレベーターに乗ることに極度の恐怖を感じます。閉じ込められる恐怖から、どんなに高層階でも階段を使うようになり、体力的な負担も大きくなっていました。
ONEGAME八千代台での不安障害支援の基本姿勢
長年の支援経験から、私たちが大切にしている不安障害へのアプローチをお伝えします。
①「否定しない」「急がせない」「比較しない」 不安を感じている本人にとって、その感覚は極めてリアルです。「気にしすぎ」「考えすぎ」という言葉は、本人の苦しみを否定することになります。ONEGAMEでは、まず利用者さんの不安を受け止め、「それはつらいですね」と共感することから始めます。また、回復のペースは人それぞれです。「もう大丈夫なはず」と急かすことなく、一人ひとりのペースを尊重します。他の利用者さんと比較することもせず、その方自身の小さな変化を認め、励ますことを大切にしています。
②「できること」から始める 不安障害では「できないこと」に目が向きがちですが、私たちは「できること」に焦点を当てます。たとえば、外出が難しい方でも、施設内の移動なら可能という場合は、そこから始めます。 Jさん(30代男性)は重度の社会不安から、最初は個室でのみ作業を行っていました。少しずつ扉を開けての作業、共有スペースでの短時間の活動と、できることを少しずつ増やしていきました。1年後には、小規模なグループ活動にも参加できるようになりました。
③ 環境調整と段階的アプローチ 不安を感じる状況を一度に克服することは困難です。ONEGAME八千代台では、環境を調整しながら、段階的に不安に向き合う機会を作ります。 例えば、人前で話すことに不安を感じるKさん(20代女性)には、最初は支援員1人の前で話す練習から始め、慣れてきたら2〜3人のグループ、そして少しずつ人数を増やしていきました。また、話す内容も最初は「昨日の夕食」など簡単な話題から始め、徐々にテーマを広げていきました。
現場で効果を実感している不安障害への具体的アプローチ
30年の支援経験の中で、特に効果が高かった不安障害への対処法をご紹介します。
① 呼吸法と筋弛緩法~「今」に戻るアンカー~ 不安が高まると、呼吸が浅く速くなり、筋肉が緊張します。これが更なる不安を生む悪循環を生みます。ONEGAME八千代台では、毎朝のプログラムとして呼吸法と筋弛緩法を実践しています。
腹式呼吸法の実践例 お腹に手を当て、鼻から4秒かけて息を吸い、お腹を膨らませる 2秒間息を止める 口から6秒かけてゆっくりと息を吐き、お腹をへこませる これを5回繰り返す パニック発作を経験するLさん(40代女性)は、この呼吸法を「不安の嵐の中の灯台」と表現しています。発作の予兆を感じた時に、この呼吸法に集中することで、症状の悪化を防げるようになりました。
漸進的筋弛緩法の実践例 手を強く握りしめる(5秒間)
一気に力を抜く(10秒間)
腕を曲げて力を入れる(5秒間)
一気に力を抜く(10秒間)
肩を耳に近づけるように上げる(5秒間)
一気に力を抜く(10秒間)
全身の主要な筋肉グループについて同様に行う
全般性不安障害のMさん(50代男性)は、就寝前にこの方法を実践することで、入眠までの時間が短くなったと報告しています。
②マインドフルネス~「考え」と「自分」を分ける練習~ 不安障害では、不安な考えと自分自身が一体化してしまいがちです。ONEGAMEでは、週に2回、15分間のマインドフルネス瞑想の時間を設けています。
「葉っぱを流す」エクササイズの実践例 目を閉じて、心の中で川をイメージする 不安な考えが浮かんできたら、それを葉っぱの上に乗せる 葉っぱが川の流れに乗って遠ざかっていく様子を想像する 「これは不安な考えであり、自分自身ではない」と認識する 社会不安障害のNさん(30代女性)は、「自分は駄目な人間だ」という考えに苦しんでいましたが、このエクササイズを通じて「それは単なる考えであり、事実ではない」と捉えられるようになってきました。
③認知の再構成~「考え方の癖」に気づく~ 不安障害の方々には、特定の認知の偏り(例:破局的思考、白黒思考)が見られることがあります。ONEGAME八千代台では、個別面談の中で、これらの思考パターンに気づき、より現実的な考え方を探る支援を行っています。
「思考記録表」の活用例 不安を感じる状況を書き出す その時に浮かぶ自動思考(考え)を記録する その考えに伴う感情と強さ(0-100%)を記録する その考えを支持する証拠と反証する証拠を探る より現実的で役立つ代替思考を考える 新しい思考による感情の変化を記録する 全般性不安障害のOさん(40代女性)は、「少しでも遅刻したら解雇される」という考えに悩まされていました。思考記録表を通じて、「遅刻は避けるべきだが、一度の遅刻で即解雇されることはまれである」というより現実的な見方ができるようになり、朝の準備の際の不安が軽減しました。
④エクスポージャー(段階的暴露)~少しずつ不安と向き合う~ 不安を感じる状況を避け続けると、不安はむしろ強くなります。ONEGAMEでは、安全な環境で、段階的に不安と向き合う練習を行います。
エレベーター恐怖症へのアプローチ例 エレベーターの写真を見る エレベーターの前に立つ ドアが開いたところまで入る(すぐに出てもOK) 支援者と一緒に1階分だけ乗る 徐々に階数を増やしていく Iさん(50代女性)は、このアプローチを6か月間続けた結果、支援者と一緒なら5階までのエレベーター利用が可能になりました。
⑤身体活動~不安のエネルギーを発散する~ 不安は体内にエネルギーとして蓄積されます。ONEGAME八千代台では、このエネルギーを健康的に発散するための身体活動を重視しています。
実践している身体活動の例 朝の15分間ウォーキング 昼食後のストレッチ 週2回のリズム体操 月1回のスポーツレクリエーション パニック障害のPさん(30代男性)は、「体を動かした日は、夜の不安が少ない」と実感しています。特に有酸素運動後は、身体的な緊張感が和らぎ、睡眠の質も向上すると報告しています。
不安障害との共存、完全な克服だけが目標ではない
私が30年の支援経験で学んだ重要なことの一つは、「不安と共に生きる術を身につける」という視点です。不安を完全になくすことではなく、不安があっても生活の質を保ち、自分らしく生きることが目標になります。
①「100%でなくていい」という価値観 多くの不安障害の方々は完璧主義的傾向があります。ONEGAME八千代台では、「80%できていればOK」「失敗も成長の糧」という価値観を大切にしています。 Qさん(40代男性)は、仕事の完璧さにこだわるあまり、提出できずに悩んでいました。「まずは下書き段階でのフィードバック」という方法を取り入れたことで、完成前の状態を他者に見せることへの抵抗が減り、作業効率が上がりました。
②「調子の波」を受け入れる 不安障害の回復は直線的ではなく、良い時期と悪い時期の波があります。ONEGAME八千代台では、調子が悪い時期も自己否定せずに受け入れ、その時にできることを行う姿勢を支援しています。 Rさん(30代女性)は、天候や体調によって不安の強さが変動することに気づき、「不安バロメーター」という自己モニタリングツールを作成。調子の良い日は新しいチャレンジを、悪い日は基本的なセルフケアを優先するという対処法を身につけました。
③「助けを求める」ことの再定義 不安障害の方々は、しばしば「人に頼ることは弱さの表れ」と考えがちです。ONEGAME八千代台では、「助けを求めることは勇気であり、自己管理能力の一つ」という視点を伝えています。 Sさん(50代女性)は、パニック発作が起きそうな時に周囲に助けを求めることに強い抵抗がありました。「ヘルプカード」(発作時の対応を書いたカード)を作成し携帯することで、必要時に言葉を発しなくても助けを求められるようになりました。
不安障害支援の実際~ONEGAMEでの一日の流れ~
不安障害のある方々にとって、予測可能な環境と明確な構造は安心感につながります。ONEGAME八千代台での一日の流れをご紹介します
9:30-10:00 朝のウェルカムタイム 穏やかな音楽と共に、静かな環境で到着 気分チェックシートの記入(不安レベルを0-10で評価) 今日の予定の確認
10:00-10:15 モーニングエクササイズ 呼吸法と軽いストレッチ 肩や首の緊張をほぐす運動
10:15-12:00 午前の作業時間 個々の状態に合わせた作業(集中作業と休憩のバランスを考慮) 15分ごとのマイクロブレイク(深呼吸や水分補給)
12:00-13:00 ランチタイム 静かな環境での食事(強制的な会話はなし) 食後の選択的活動(休憩、軽い散歩、雑談など)
13:00-14:50 午後の活動時間 月曜:グループディスカッション(不安管理のテーマ) 火曜:創作活動(アート、音楽など) 水曜:生活スキルワークショップ 木曜:リラクゼーション実習 金曜:社会体験活動(段階的に範囲を広げる)
14:50-15:00 デイクロージング 今日の振り返り 明日の予定確認 帰宅前の呼吸法 これらの構造化されたプログラムは、不安障害のある方々に予測可能性を提供し、「何が起こるかわからない」という不安を軽減します。同時に、個々の状態に合わせて柔軟に調整することも重視しています。
ご家族・支援者へのメッセージ~「伴走者」としての姿勢~
不安障害のある方を支える家族や支援者の方々へ、ONEGAME八千代台からのメッセージをお伝えします
①あなた自身のケアを忘れずに 支援者自身が疲弊していては、良い支援はできません。ONEGAMEでは、スタッフ間でのピアサポートや定期的なセルフケアの時間を大切にしています。「自分を責めない」「完璧を求めない」というルールは、利用者さんだけでなく、支援者自身にも適用されます。
②「治す」より「共に歩む」 不安障害の方を「治そう」「変えよう」とするのではなく、その方のペースで共に歩む姿勢が大切です。「この状況をどう乗り越えるか、一緒に考えましょう」というスタンスで接することで、信頼関係が生まれます。
③小さな変化を見逃さない 不安障害からの回復は、時に非常に小さな変化から始まります。「今日は5分長く外にいられた」「初めて電話で予約ができた」など、日常の小さな勇気と成長を見逃さず、共に喜ぶことが大切です。
まとめ~希望を持って不安と向き合うために~
私が30年間、不安障害のある方々と共に歩んできた経験から言えることは、「回復は必ず可能である」ということです。不安障害は、適切な支援と本人の努力によって、必ず良い方向に変化していきます。 完全に不安がなくなることが目標ではなく、不安と上手に付き合いながら、自分らしい人生を送ることが真の回復です。ONEGAME八千代台で見てきた多くの利用者さんが、少しずつ自分の可能性を広げ、豊かな人生を取り戻していく姿は、支援者である私たちにとっても大きな喜びであり、学びとなります。 不安という荒波の中で溺れそうになっている方、そしてそれを支える方々へ。一人で抱え込まないでください。専門家のサポートを受けながら、一歩ずつ前に進むことで、必ず道は開けます。小さいかもしれませんが、その歩みを、ONEGAME八千代台はこれからも支え続けていきたいと思います。
みんなのかまちゃんより