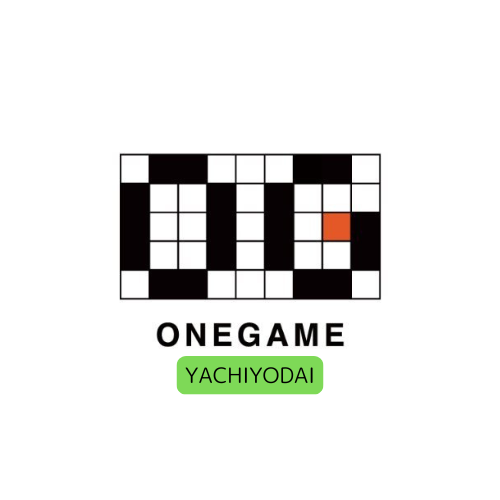みなさん、こんにちは!ONEGAME八千代台のサービス管理責任者の「かまちゃん」です。30年以上にわたって精神障害を持つ方々と共に歩んできた経験から、今日は「運動療法」について皆さんにお伝えしたいと思います。
長年の支援の中で、薬や対話だけでなく「体を動かすこと」がもたらす素晴らしい変化を何度も目の当たりにしてきました。利用者さんの笑顔が増え、自信を取り戻していく姿は、私たち支援者にとっても大きな喜びです。理論だけでなく現場の実体験に基づいた「運動療法」の効果と実践方法をお話ししましょう。
精神障害と運動の関係性:現場から見えてきたもの
就労継続支援B型事業所で日々利用者さんと接していると、心と体の密接な関係性を実感します。座りっぱなしの生活が続くと気分も沈みがちになり、逆に適度な運動をすると表情が明るくなる——そんな変化を毎日見ています。 医学的に説明すると、運動には以下のような心への効果があります
・「幸せホルモン」の分泌促進
エンドルフィンやセロトニンなどの分泌を促し、気分を高めます
・ストレスホルモンの減少
コルチゾールなどのストレスホルモンを減らします
・認知機能の向上
集中力や記憶力が改善します
・睡眠の質の向上
深い睡眠を促し、不眠症状を和らげます 特に就労の場面では、運動によって集中力が高まり、作業効率が上がることも実感しています。
利用者さんの状態別に見る運動療法の効果
・うつ状態の方への効果 「何もする気が起きない」「朝起きるのがつらい」という利用者さんに、まずは短時間のウォーキングからスタートしていただいた例があります。
Cさん(40代男性)は、重度のうつ病で3年間引きこもり状態でした。ONEGAMEに来所し始めた当初は、椅子に座っているだけでも疲れると話していました。まずは施設内の短い距離の歩行から始め、徐々に外周りのウォーキングへ。3ヶ月後には「朝、少し早く目が覚めるようになった」と報告してくれました。今では週3日の通所が安定し、簡単な作業にも取り組めるようになっています。
・不安症状の強い方への効果 パニック発作や強い不安に悩む利用者さんには、呼吸を意識した運動が効果的です。
Dさん(30代女性)は、外出時にパニック発作を起こすことが多く、ONEGAMEでも最初は落ち着かない様子でした。体操の時間に簡単な呼吸法とストレッチを組み合わせたエクササイズを取り入れたところ、「体が温かくなると落ち着く」と気づかれました。今では自分で不安を感じた時に、呼吸を整えながらその場でできるストレッチを行い、症状をコントロールできるようになっています。
・統合失調症の方への効果 陰性症状(意欲低下、引きこもりなど)が強い統合失調症の方々にも、運動は大きな効果を発揮します。
Eさん(50代男性)は、長年統合失調症の陰性症状に悩まされ、日中もベッドで過ごすことが多い状態でした。ONEGAMEでのグループ体操に誘ったところ、最初は消極的でしたが、他の利用者さんと一緒に体を動かす中で少しずつ表情が変わってきました。6か月後には自ら「今日は何をしますか?」と体操の時間を楽しみにするようになり、日常会話も増えてきました。
ONEGAMEで実践している運動プログラム
30年の経験から、以下のような運動プログラムが特に効果的だと感じています
① 朝のラジオ体操 単純ですが侮れないのが「ラジオ体操」です。利用者さんの状態に合わせて、座ったままでもできる動きから始めます。全身をまんべんなく動かすことで、体が目覚め、一日のスタートが切りやすくなります。ONEGAMEでは毎朝10時に全員で行い、一日の活動のリズムを作っています。
② グループウォーキング 週2回、施設周辺を20〜30分かけて歩きます。季節の変化を感じながら、無理のないペースで歩くことを大切にしています。会話をしながら歩くことで、自然と社会性も育まれます。途中で疲れた方は休憩したり、距離を短くしたりと、個々の状態に合わせて調整しています。
③ 軽いボール運動 リハビリボールを使った簡単なキャッチボールや、風船バレーなど、楽しみながらできる運動を取り入れています。特に集団でのゲーム形式は、自然と笑顔が生まれ、コミュニケーションの機会にもなります。
④ 音楽に合わせた体操 リズムに合わせて体を動かすことで、自然と気分が高まります。座ったままでもできる簡単な振り付けから始め、徐々に立って行う動きも増やしていきます。音楽の選曲は利用者さんからのリクエストも取り入れ、参加意欲を高めています。
支援現場での運動導入の工夫とコツ
私の福祉経験30年から得た、精神障害を持つ方々への運動支援のコツをお伝えします
① 無理強いしない、でも諦めない 「やりたくない」という気持ちは尊重しつつも、「今日は見学だけでも」と誘い続けることが大切です。見学から参加へ、短時間から少しずつ長く、と段階的な参加を促します。
② 成功体験を積み重ねる 「できた!」という体験が次への意欲につながります。必ず達成できる簡単な目標から始め、小さな成功を一緒に喜びます。ONEGAMEでは「今日は5分続けられましたね!」など、具体的な成果を伝えるようにしています。
③ 集団の力を活かす 一人では続かなくても、仲間と一緒なら頑張れることがあります。「皆で一緒に」という雰囲気づくりを大切にし、お互いを励まし合える関係性を育んでいます。
④ 季節や行事に合わせた運動イベント 単調になりがちな運動も、季節の行事に合わせることで新鮮さを保てます。ONEGAMEでは、春のお花見ウォーキング、夏の水中体操、秋の紅葉散策、冬の室内運動会など、季節ごとの特別プログラムを企画しています。
⑤家族や主治医との連携 効果を持続させるには、家庭での継続と医療との連携が欠かせません。ご家族にも簡単にできる運動方法をお伝えし、主治医にも運動の内容と効果を報告・相談しています。
運動を通じて見えてきた「回復」の姿
30年の支援の中で、運動がきっかけとなり大きく変化した方々がたくさんいます。特に印象的なのは、以下のような変化です、
・自己効力感の向上 「自分にはできる」という感覚を取り戻すことが、精神障害からの回復の大きな一歩です。運動で体を動かし、少しずつできることが増えていく体験は、他の活動への自信にもつながります。
・社会性の回復 個人で行う運動よりも、グループでの活動を通じて自然と会話が生まれ、人との関わりを取り戻していきます。ONEGAMEでのウォーキンググループから地域のウォーキングイベントに参加するようになった利用者さんもいます。
・生活リズムの改善 決まった時間に体を動かすことで、睡眠覚醒リズムが整い、生活全体が安定します。「朝起きられるようになった」という声は、運動を始めた利用者さんからよく聞かれます。
現場からの提言:B型事業所での運動療法導入のために
精神障害者の就労支援施設でも、運動療法は十分に取り入れられる価値があります。そこで30年の経験から、以下のような提言をさせていただきます、
①日課への組み込み 「できる時にやる」ではなく、日課として定時に行うことで習慣化しやすくなります。ONEGAMEでは朝の活動開始時と昼食後の2回、15分ずつの運動時間を設けています。
② 支援者も一緒に楽しむ 「やらせる」のではなく「一緒にやる」姿勢が大切です。支援者自身が楽しんで体を動かすことで、利用者さんも参加しやすくなります。
③成果の「見える化」 体重や血圧の変化、継続日数などを記録し、視覚的に成果がわかるようにすることで、モチベーション維持につながります。ONEGAMEでは「元気カレンダー」で運動参加日に花マークを貼り、継続を可視化しています。
④地域資源との連携 地域のウォーキング大会や体操教室など、外部の資源と連携することで、活動の幅が広がります。ONEGAMEでは地域のラジオ体操の会や、市のスポーツイベントにも積極的に参加しています。
まとめ:「動く喜び」が回復の原動力に
30年間、精神障害を持つ方々と共に歩んできた中で、「動く喜び」を取り戻すことが回復の大きな力になることを実感してきました。薬物療法や精神療法と並行して、運動療法を取り入れることで、より豊かな回復の道が開けます。 ONEGAMEでは今後も、一人ひとりの状態に合わせた運動プログラムを提供し、「体を動かす楽しさ」を通じて、利用者さんの回復と社会参加を支援していきたいと考えています。小さな一歩から始める運動が、やがて大きな変化をもたらす——それが30年の支援現場から得た確信です。皆さんの施設でも、ぜひ運動療法の可能性を探ってみてください。
ではまた、みんなのかまちゃんより